
No.159「【通勤災害】どこまでが通勤か」について
目次
〜とよひらの社労士通信No.159〜「【通勤災害】どこまでが通勤か」について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

昨日は長男、今日は次男の卒業式に出てきました
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、「【通勤災害】どこまでが通勤か」についてのお話しです。
ご存じの方には、当たり前の内容かもしれませんが、おさらいいただければ幸いです。
【通勤災害とは】
・通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
(1)住居と就業場所との間の往復
(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
(3)就業場所から他の就業場所への移動
を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
移動中の災害でも、出張に係る移動は、基本的に通勤ではなく業務とみなされますので、「通勤災害」ではなく「業務災害」となります。
【通勤の逸脱または中断とは】
・通勤の途中で逸脱または中断があると、その後は原則として通勤とはなりません。
・「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、
・「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の途中で映画館を見る、飲酒するなどをいいます。
しかし、通勤の途中で、経路近くの公衆トイレを使用、ジュースを購入するなどのささいな行為は、逸脱、中断とはなりません。
・日常生活上必要な行為をやむを得ない理由で、最小限度の範囲で行う場合は、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となります。
例えば、
・日用品の購入
・職業訓練、教育訓練
・選挙権の行使
・病院
・親族の継続的な介護
などは、日常生活上必要な行為の例として挙げられます。
これらの行為後、通常の通勤経路に戻った後は、通勤災害の対象となり得ます。
当然ながら、逸脱の間(例えば、日用品の購入の最中)にケガをした場合は、通勤災害の対象外です。
【会社の責任について】
・通勤災害は、業務中の災害に比べれば、使用者(会社)に直接の責任がある訳ではありません。
しかし、従業員が起こした通勤時に交通事故を起こした場合、
・使用者責任(民法715条)
・社用車の場合は、運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)
が該当する可能性があります。
「事業主が禁止しているのに、マイカー通勤をしていた」という状況では、事業主の責任が否定される判例がありますが、
マイカー通勤をOKしていれば、基本的に「使用者責任」が発生することになります。
・マイカー通勤を許可する場合は、自動車保険の加入や内容について、会社としてもしっかり把握しておくことをおススメします。
【通勤災害の補償・手続について】
・通勤災害では、業務災害と同じように、労災保険から療養の給付(病院代)、休業補償を受けることができます。
・休業の場合、待機の3日間については、業務災害では事業主が補償する義務がありますが、通勤災害では事業主に補償の義務はありません。
・また、業務災害時に労基署に提出する「死傷病報告」の提出は、通勤災害にはありません。
No.159〜「【通勤災害】どこまでが通勤か」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【通勤災害】どこまでが通勤か」について、お話しました。
通勤災害は、業務災害に比べると従業員の問題と考えがちです。
徒歩や公共交通機関の通勤であれば、概ねそれで問題ありませんが、
特にマイカー通勤の場合は、会社にも使用者責任が生じますので、安全運転教育や任意保険の加入などについて、しっかりと周知いただければと思います。
引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-
当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。
<社会保険労務士法人とよひらについて>
・対応可能な業務
・日々の業務対応のイメージ
・料金プラン
・お問い合わせ

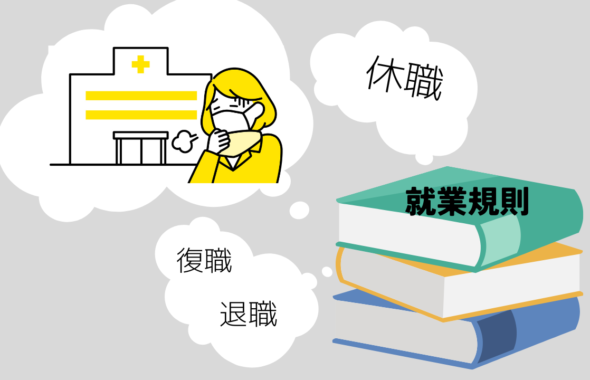
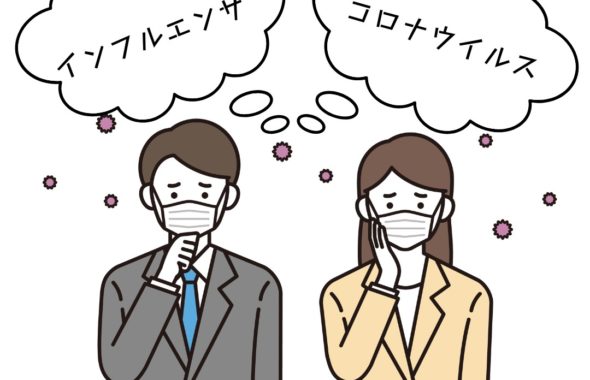




この記事へのコメントはありません。